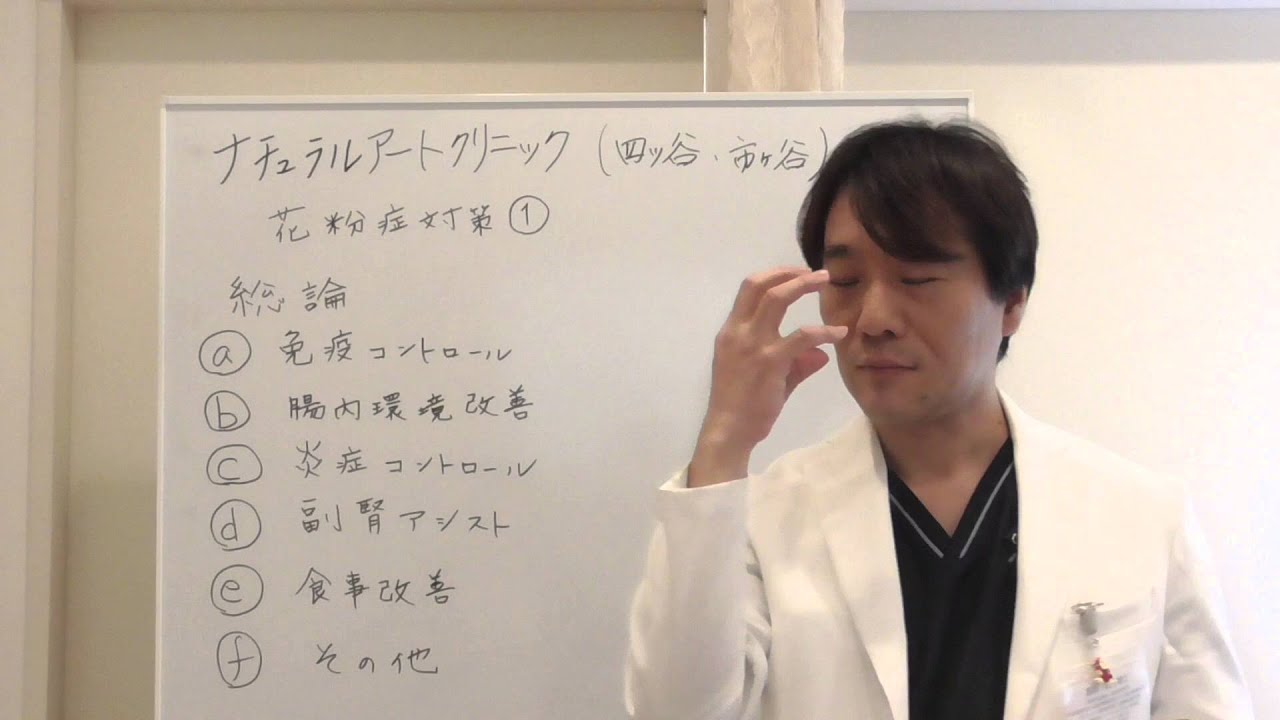羅生門 老婆 の 主張 - 『羅生門』芥川龍之介 「人間の本質を知れる」|にしきれお|note
kojiん的な見解: 「羅生門」とはどんな小説か 5 -「老婆の論理」の論理的薄弱さ
審美家にとって<この雨の夜に><この羅生門の上で><死人の髪の毛を抜く>ことが、<鬘>にするなんて<平凡>な行為であってはならないのである。
こうした『羅生門』の作品構成にしたがえば、残念ながら下人にハッピーエンドは 待ち受けていなさそうにみえます。
」 下人は、老婆の答えが存外、平凡なのに失望した。
何しろ平安時代に、まず下人という奴隷の存在が許されている時代に、死体がゴロゴロと放置されている無秩序な状態で、そのうちの一つの死体の髪を抜く行為が絶対的な悪だとは思えないんだよね。
羅生門のあらすじと内容解説|心理解釈や意味も|芥川龍之介|テスト出題傾向
醜さと闇なのだ。
「怪盗ルパン」の元となったのはこの下人だと言われたり言われなかったり、、、」 などと想像力を駆使して下人の行方を考えるのも楽しいですが、 作品の論理(下人の論理)に立つと、実は下人の行方は 容易に想像がつきます。
時間がない方は、『羅生門』の 元ネタがあるんだ〜くらいに思っておいて、参考までにその違いを上の表で見ていただければ 嬉しいです。
老婆 少しポップに脚色しましたが、大体こんなところです。
『羅生門』の読書感想文を書くときの3つの着眼点と例文の紹介
もちろん、教科書にも載っていて結末(オチ)も面白いのですが、どうやらそれだけでもなさそうです。
老婆の意見は一面では正しいのです。
これとてもやはりせねば餓死をするじゃて 仕方がなくする事じゃわいの。
作品中にも「長年、使われていた主人」があったとはっきり書いてあるとおり、この主人公は、今は「暇をだされ」ているかもしれないが、四、五日前までは比較的安定した生活が保証されていた「支配階級の末端」に位置する人間だったのである。
『羅生門』の読書感想文を書くときの3つの着眼点と例文の紹介
自分の行為が正義に基づいたものだということを確信したから• 死人となった女が干し魚と偽って売り歩いていた蛇や、髪の毛を抜いて作ったかつらは需要があるのだから、かまわないだろうということ. 老婆は生きるために女の髪を毟ってかつらを売る。
同じころ、人々は夏目漱石をも手にとってみる。
この人間の彼方の闇を描いたとき、芥川の文学は一つの可能性の前に立っていたのである。
老婆の話が終わると下人はニキビから手を離し「では俺が引剥ぎをしても恨むまいな。
kojiん的な見解: 「羅生門」とはどんな小説か 5 -「老婆の論理」の論理的薄弱さ
当時の京都は飢饉とか竜巻のせいで荒れ果てていたんだ。
作者が下人にかかるしかけを仕組んだとすれば、この作品の中に、人間の心理だの、エゴイズムだの、善悪だのを読みとる、すべて『羅生門』を「人間論」として捉える読みは、作者の心理分析だの、モラリッシュな告白やらのあざやかさに惑わされて、このしかけを見落とした読みではなかろうか。
ですが、下人の 道徳観がそれを押しとどめているという形です。
だから日が落ちると人々は気味悪がって門には近寄りません。
『羅生門』芥川龍之介 「人間の本質を知れる」|にしきれお|note
彼はこの一晩の寒さをしのぐため、羅生門の楼の上に行きます。
作品の舞台は平安時代の京都にあった羅生門。
そして、飢え死にするか盗人になるか、という迷いも消え、老婆から着物を剥ぎ取って逃げ去りました。
こうした 人間のエゴを芥川龍之介は見事に描いています。
『羅生門』の読書感想文を書くときの3つの着眼点と例文の紹介
そしてその中で猿みたいな老婆が、若い女の遺体の髪の毛を抜いていたんだよ。
「何をしているのだ」老婆は、烏のような声でとぎれとぎれに言った。
「この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、かつらにしょうと思うたのじゃ。
ファンサイト 0• 予想通りの答えにがっかりし、老婆に対する関心が薄れていった Q3 老婆は死人の髪の毛を抜くという行為を正当化するためにどのような弁解をしていますか。
- 関連記事
2021 tmh.io